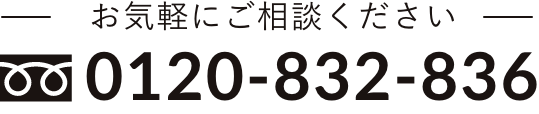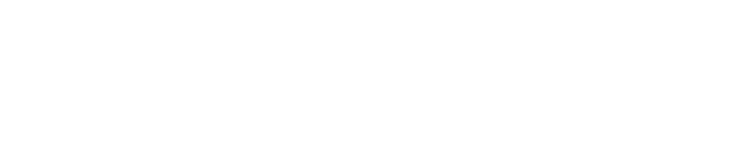2026年の住宅業界の変化|補助金や税制まで大予測!
目次
1.2026年の住宅補助金
2026年の住宅補助金の詳細は、今のところ不明です。近年の住宅補助金の大部分は補正予算が占めており、補正予算の編成・成立は11~1月頃に行われることが多く、補正予算の編成と成立の段階で大枠について知ることができます。また、住宅補助金の内容は例年2~3月頃に確定することが多いです。
但し、今年度と来年度の予算の概算要求から、変化を見つけることができます。各省庁の発表資料から予算の増減や施策内容を見ることができるため、補助金の有無や対象要件になりそうな項目を見つけることもできます。例えば、環境省の令和7年度の概算要求と令和8年度の概算要求を見比べてみると大きな違いがわかります。一つは「地域区分」の追加、もう一つは「再エネを除く一次エネルギー消費量削減率」の明確化です。
令和8年度の概算要求を見ると、地域区分(気候に合わせて建築物の省エネ基準を定めた区分)が明記され、戸建住宅では1~3地域(主に北海道や東北など)と4~8地域(主に北海道や東北以外)で10万円の差額があります。また、再エネを除く一次エネルギー消費量削減率も以前は20%以上としていたところ、30%以上も記載されています。これらを考えると、2026年の住宅補助金では、地域や一次エネルギー消費量削減率によって補助額が変わる可能性があります。
また、令和7年度の概算要求を含め以前までは、再エネ設備の導入やエネルギー消費量削減率について、予算請求の段階で地域や立地等を考慮した記述はあまり見られませんでしたが、令和8年度では概算要求の段階で寒冷地や多雪地域、都市部狭小地等に関する記載がある点も変化が見られます。
住宅補助金は、補正予算が閣議決定された段階(11~12月頃)で大枠について知ることが出来ますが、予算成立を前提としていることや要件が実施前に変更となることもあります。そのため、2~3月頃にならないと正確な情報ではない可能性もあるため、注意が必要です。
2.住宅関連の減税
令和8年度税制改正要望事項を見ると、2026年における住宅関連の減税について傾向がわかります。但し、これらは決定ではなく要望であるため、最終的な決定は閣議決定後に国会に提出されてから決まります。但し、例年では12月中旬頃に発表される税制改正大綱から大きな変更なく可決されています。
住宅ローン減税
2026年からの住宅ローン減税は、制度の延長もしくは新しい制度に変わると思われます。これまでをみると、税制改正は記載されている施策の背景に関連が高いものが要件等に盛り込まれることが多くあります。今回は「世帯構成」「既存住宅ニーズ」「災害ハザードエリア」の記載があり、新しい制度になると思われます。
これまで子育て世帯や若者夫婦世帯の借入上限額が高い傾向でしたが、世帯による差をなくす、もしくは小さくする可能性があります。また、既存住宅と新築住宅で上限額に大きな差がありましたが、この差も既存住宅の住宅性能によって引き上げる可能性もあります。
さらに、これまで立地要件については特に指定はありませんでしたが、土砂災害特別警戒区域や災害危険区域、浸水想定高さが高い区域や市街化調整区域など立地要件で控除額が低くなる、もしくは控除がなくなる可能性があります。これらの要件は、既に住宅補助金の要件の一部となっているため可能性は高いと思われます。
固定資産税
固定資産税は、新築住宅に対する税額を1/2に軽減する(戸建て:3年間、マンション:5年間)特例措置を2年間延長する要望を出しています。また、認定長期優良住宅の場合、現行では控除額が増え、期間も2年ずつ長くなっていますが、こちらも2年間延長する要望となっています。
登録免許税
土地の所有権移転時にかかる登録免許税は、現在の特例措置を3年間延長する要望を出しています。
2026年以降に入居予定の場合、立地や住宅性能等によって住宅ローン減税の恩恵が受けられない、もしくは控除額が少なくなる可能性が十分考えられます。これから住宅を購入・建築する場合は、住宅性能や立地について慎重に検討する必要があると言えます。
3.住生活基本計画
住生活基本計画とは、住生活基本法に基づき国民の住生活の安定と向上のための基本的な目標と施策を定める国の計画と都道府県や市町村が地域の実情に合わせて策定する計画です。概ね5年毎に見直しがされており、住宅の補助金や減税等についても深く関わりがあり、建築分野の在り方の検討にも影響します。
次回の見直しは既に始まっており、2026年3月に閣議決定される予定で、11月頃に中間のとりまとめが発表される予定です。既に中間とりまとめ(案)は公表されており、主に11項目において今後10年間の方向性と2050年の姿をまとめています。また、等時に建築分野においても様々な議論が交わされています。
住宅性能や利用価値の評価
日本において、空き家問題を含む住宅関連の問題の鍵を握る要素の一つが「既存住宅の循環」です。既存住宅は、新築と比べて安価である一方、住宅性能やリフォームの必要性などわからないことが多く不安なため、選ばれにくいのが現状です。これらを解消するために、これまで住宅検査(インスペクション)やリフォーム、維持管理履歴の普及・推進をしてきましたが、思うような成果に繋がっていませんでした。
そのため、これまで以上に住宅性能と利用価値に着目し、高い住宅性能や適切な維持管理がされた住宅が適切に評価され、さらに金融機関等とも連携しインセンティブが働く仕組みを構築する必要性に言及しており、具体的な方法としてリバースモーゲージ等の「住宅資産の流動化の推進」「残価設定型の住宅ローン」などが挙げられています。
また、住宅性能表示制度や長期優良住宅の普及・促進にも言及しています。現在出ている情報の中でも、住宅性能や維持管理について言及されているため、これから住宅を購入・建築する場合は設計・建設性能評価の取得や長期優良住宅の認定を受けていると、将来的にメリットを一層享受できる可能性があります。
アフォーダブルな住宅取得
土地価格や建築費の高騰に伴い、住宅価格が年々上昇しています。そのため、アフォーダブルな住宅(入手可能な価格の住宅)を目指し、住宅取得資金の安定確保と売却の円滑化が必要としています。頭金の積立支援、賃料代わりの住宅ローン返済負担、住み替え時に残債が足かせにならない住宅ローンなどに言及しています。
今後は、単純に住宅ローンを借りて返すだけではなく、様々な選択肢が考えられる時代が来るかもしれません。
建築物のライフサイクルカーボン(LCCO2)
ライフサイクルカーボンとは、建築設備などの製造から輸送、建築、使用、修繕、解体に至るまでの温室効果ガスの排出削減を目指す取り組みが検討されています。何年も前から議論されており、ビルや商業室など規模の大きい建物から開始し、最終的に戸建住宅でも対応が必要になる予定です。
まだ具体的な方針については検討されていますが、住宅の性能と同じく第三者評価や表示の制度が実施されることも十分考えられます。また、補助金や減税、価値評価の要素となる可能性もあります。将来を見据えるのであれば、省エネ性が高い住宅(断熱性やエネルギー消費量削減率が高い住宅)を取得することで将来的なメリットを受けられる可能性があります。
様々な情報を見ると、断熱性が高くエネルギー消費量も少ない住宅や長期優良住宅の認定、住宅表示制度の活用が今後重要になると考えられます。既にある制度を活用し、省エネ性の高い住宅を取得することで将来の役に立つ可能性があるため、今後住宅を検討する人はこれらの制度も併せて検討すると良いかもしれません。
4.一次エネルギー消費量等級の増設
一次エネルギー消費量等級とは、一次エネルギー消費量(住宅などの建物が1年間に消費する想定エネルギーの総量を数値化したもの)を省エネ基準と比べてどれだけ削減できるか示したものです。これまでは等級6が最高でしたが、省エネ性能の向上に伴い等級7と等級8が新たに創設され、12月1日より施行されます。
2025年の住宅補助金における一次エネルギー消費量等級の要件は、等級6(削減率20%以上)もしくは削減率35%以上でしたが、新たに等級7が創設されたことにより、一次エネルギー消費量の要件が細分化される可能性があります。また、これまでは等級6が最高で比較的クリアし易い基準でしたが、等級8は省エネ性を大幅に高める必要があるため、省エネ性について比較する際に大きく役立ちます。
現在では、等級4(省エネ基準)が最低基準ですが、2030年までには等級6が最低基準に法改正される予定です。そのため、もし現在住宅の建築を検討している場合、新しい等級(7や8)で検討することをおすすめします。
5.建築確認申請
建築確認申請とは、建物を建築する前に、建築計画が建築基準法等に適合しているか建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けるものです。確認済証を受け取ってから建築開始となるため、交付前の着工や確認済証のない建築物は違法となります。
法改正の影響により、今年は多くの地域で申請から交付まで約3か月かかっています。そのため、住宅建築を予定している場合、プラン決定から引き渡しまで早くて8か月(申請準備1か月+申請3か月+工期4~5か月)ほど掛かると見込んでおいた方が良いでしょう。さらに、住宅の補助金の申請は期日や予算が決まっており、基本的に確認申請が出ていなければ予算の確保もできず、2026年の要件も詳細は不明なため、早めの計画がポイントになります。
6.よくある質問
2026年の住宅の補助金はいくら貰える?
2026年の住宅の補助金は、現時点で詳細は発表されていません。例年では、11~1月の補正予算の編成・成立時に大枠が判明します。実際の細かな要件などは、補正予算成立の段階ではわからないこともあるため、補助事業のホームページ開設後に確認することが大切です。
2026年の住宅ローン減税は?
2026年からの住宅ローン減税は、制度の延長もしくは新しい制度に変わることが予想されます。税制改正は改正要望事項に記載されている施策の背景に関連が高いものが要件に盛り込まれることが多くあります。今回は「世帯構成」「既存住宅ニーズ」「災害ハザードエリア」の記載があり、新しい制度になると思われます。
2026年の固定資産税は?
2026年の固定資産税は、令和8年度税制改正要望事項によると新築住宅に対する税額を1/2に軽減する(戸建て:3年間、マンション:5年間)特例措置を2年間延長する要望を出しています。また、認定長期優良住宅の場合、現行では控除額が増え、期間も2年ずつ長くなっていますが、こちらも2年間延長する要望となっています。