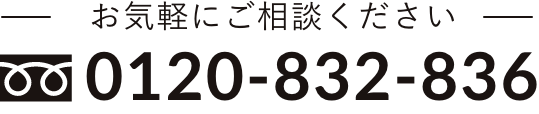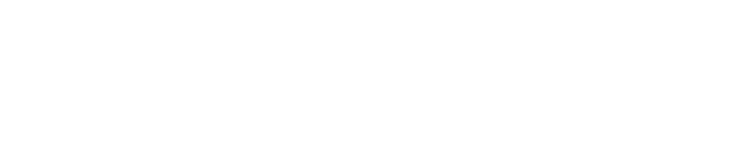メンテナンスは大変?全館空調のシステム選びとメンテナンスの関係
目次
全館空調とは
全館空調とは、住宅全体の空調管理を行う冷暖房システムです。リビングや寝室、廊下、トイレまで、家中すべての空間の温度を一定に保つことができるのが特徴です。特に北海道や高気密・高断熱住宅で導入されるケースが増えており、家庭用エアコン1台で夏の暑さも北海道の冬の寒さも乗り越えることができます。
全館空調は、1台または複数の空調ユニットがダクトや風道を通じて各部屋に空気を送るため、部屋ごとにエアコンを設置する必要がなく、見た目もスッキリし、温度差のない快適な室内環境を実現し、ヒートショックのリスク軽減にもつながります。また、空間ごとに個別のエアコンを使うよりも、エネルギー効率が良いです。
全館空調の仕組みと特徴
全館空調は、天井裏・床下・空調室などに設置された空調機器が、ダクトや風道を介して家中の各部屋に冷暖房された空気を供給する仕組みです。全館空調システムの特徴は、空調機器を1~2台を使用し、風の通り道となるダクトや風道を通り、通気口から各部屋に冷風や温風が入ることです。また、空気を送るファンを使うこともあります。
全館空調では、空調設備を床下や屋根裏などに設置して空調室を設けない場合と、空調ボックスや空調室を設けて、その中に空調設備を入れる場合の2パターンが存在しています。
一般的なルームエアコンとの違い
全館空調とルームエアコンの違いは、主に冷暖房の範囲と温度ムラです。全館空調では、家中が一定の温度になるように設定されていますが、個別エアコンでは決められた範囲の温度調整を行います。また、全館空調では空調設備が隠れて設置されキレイな一方、個別エアコンよりもメンテナンスが必要になる場合もあります。
全館空調に必要なメンテナンスとは?
全館空調は、快適な室内環境を年間を通して維持できる反面、その性能を持続させるためには定期的なメンテナンスが必須です。特に、フィルターの詰まりやダクトの汚れ、熱交換器の性能低下は、冷暖房効率や空気の清浄性に直結します。また、メンテナンスの頻度や対象範囲は全館空調のシステムによって大きく異なります。
フィルター掃除の重要性と手順
全館空調のフィルター掃除は、最もメンテナンスが必要で快適さを左右する要素です。全館空調のフィルターは、空調設備や空調室などの吸気口付近にあります。空気を吸い込む箇所にフィルターがあり、ほこりなどを取り除く役割を果たすとともに、空気を循環させるために必要な空気量を取り込む場所でもあります。
全館空調の中でも最も汚れやすいパーツがフィルターです。フィルターが詰まると、空気の流れが悪くなり、冷暖房効率の低下、騒音の増加、電気代の上昇、さらにはアレルギーの原因になる場合もあります。
【掃除の目安】
空調設備:1~3か月に1回
空調室(吸気口):2週間~1か月※ほこりが溜まったら
【掃除の手順】
1.電源を切る
2.吸気口からフィルターを取り外す
3.掃除機でホコリを吸い取る
4.水洗い
5.完全に乾かしてから再装着する
※掃除の目安や手順は、システムによって異なります。必ずメーカーに確認しましょう。
空調室のフィルターは、レンジフードのフィルターなどで代替できる場合もあるため、掃除せずに交換すると楽です。また、多くの機種はフィルター掃除をユーザーが行える設計ですが、2階天井や床下エアコンなど難しい場合は無理せず業者に依頼するのが安全です。自分で掃除・交換する場合は年間数千円、業者に依頼すると数万円かかります。
ダクト掃除はシステム次第
ダクトや風道は、冷風や温風を各部屋へ運ぶ空気の通り道ですが、普段は目に見えない部分です。そのため、ホコリやカビなどが蓄積すると空気の質が悪化しニオイの原因となることがあります。
基本的にダクト掃除はメーカーが行う以外に方法はありません。ダクトの清掃そのものは可能な業者もありますが、ダクトを空調設備と繋げ再配置するためには、各空調システムへの理解が必要となるためメーカーに問い合わせる必要があります。また、使用しているダクト自体が清掃ではなく交換を前提としている場合もあります。
全館空調システムにおけるダクトや風道の掃除、交換についてはシステムによって全く異なります。メンテナンスが基本不要な場合もあれば、数年に1回の清掃、交換が必要なシステムもあります。特に、空調室を設けていないシステムや冷暖房停止時にダクト内の空気が循環しないシステムには注意が必要で、ダクトレスのタイプでも断熱材や他の建材などに直接影響が出る可能性もあるため、システム選びを慎重に行う必要があります。
換気システムの点検項目
全館空調と換気システムが一体になっているシステムもありますが、多くの場合は別のシステムとなっています。別のシステムの場合でも、換気システムのメンテナンスは全館空調の快適性に繋がります。特に、熱交換付きの換気システムの場合は光熱費にも影響が出る可能性があります。
【掃除の目安】
3か月に1回以上(熱交換エレメントは2年毎に点検・交換)
【主な点検内容】
・吸気・排気フィルターの確認と清掃
・吸気フードやダクトの詰まりチェック
・熱交換素子の破損や劣化の有無
・ファンモーターの動作状況
換気システムは、第1種・第2種・第3種の3つの種類があり、さらに製品が様々あるため、メンテナンス頻度や手順については取扱説明書を参考にしましょう。全館空調に大きく影響するものは「換気量」「熱交換エレメント」です。
換気量:換気量(排気量)が多いと、室内の温かい(冷たい)空気がすぐ外に流れてしまうことになります。すぐに室内の空気を入れ替えたい場合は排気量を多くしても問題ありませんが、常時排気量を多くすると室内が快適な温度に保ちにくく、光熱費も上がる原因となるため、設定が正しいか確認しましょう。
熱交換エレメント:熱交換エレメントとは、排気と給気で熱の交換するもので主に第一種換気で利用されています。この交換は、温度だけではなく湿度も交換するものもあります。そのため、エレメントに異常があると温度・湿度に影響があるため、必ず確認しておきましょう。
加湿機能つき機種のメンテナンス
全館空調と加湿機能が一体になっているシステムもありますが、多くの場合は別のシステムとなっています。冬季の乾燥対策として加湿機能を搭載した全館空調は魅力的である一方、加湿器はカビや雑菌が繁殖しやすい装置でもあります。そのため、加湿ユニットの定期的なメンテナンスは欠かせません。
【主なメンテナンス項目】
・加湿用フィルターの洗浄・交換
・水タンクや配管の洗浄(ぬめりや水アカ除去)
・除菌カートリッジの定期交換(機種による)
【頻度の目安】
・加湿フィルターは1〜2か月に1回の掃除、1年に1回交換
・除菌カートリッジは半年に1回の交換推奨
適切にメンテナンスされていない加湿機能は、逆に空気中に雑菌をまき散らしてしまうリスクがあります。清潔な湿度管理のためにも、定期的な確認とケアが重要です。
年に何回必要?全体のスケジュール目安
全館空調のメンテナンスは、年間を通じて計画的に行うのが理想です。
フィルター清掃・交換(空調室):2週間~1か月に1回
フィルター清掃(空調設備):1か月に1回
換気設備の清掃:3か月に1回
その他については、全館空調システムによって大きく異なるため、メーカーの推奨する方法で行いましょう。
メンテナンス時に一緒に確認した方が良いこと
換気量:換気量の多い設定になっていないか。
設定温度:設定温度が季節によって適切な設定になっているか。
運転モード:空調設備が、季節によって推奨される運転モードになっているか。
風向:空調設備、通気口などの風向が正しい位置になっているか。
風量:冷暖房の風量が推奨される風量で設定されているか。
設定温度を除き、普段あまり気にしないことも多いため、メンテナンス時に一緒に確認すると良いでしょう。
メンテナンスから考えるシステム選びのポイント
メンテナンスから全館空調システムを選ぶとき、重要になるのが結露・ホコリ・カビの対策です。全館空調のメンテナンスで最も高額になるのはダクトや風道の清掃や交換のため、それらのスペースでホコリを溜めず、結露を防止し、カビの対策を講じることが大切になります。
空気の滞留
空気が滞留すると、ダクトや風道でホコリや湿気が溜まりやすくなるため汚れやカビの発生の原因となります。夏や冬は、冷暖房を稼働させるためダクトや風道は常に空気が循環している状態です。一方で春や秋など冷暖房を止める時期は、システムによって空気が循環しない状態となるため、ほこりや湿気が溜まりやすくなります。
空調設備の設置環境
空調設備がどこに、どのような状態で設置されているかによって、ダクト内のホコリや結露の発生リスクが異なります。多くの場合、空調設備は小屋裏・床下・階間などの普段目に見えない場所、もしくは1階や2階に設けられた空調室や空調箱(空調設備を覆うボックス)の中に設置されています。
空調室・空調箱:基本的に、空調室や空調箱の吸気口にフィルターが設置されており、空調設備に空気が取り込まれる前にホコリをほとんど吸着します。また、空調室や空調箱の内部は室内の温度に近く空気も循環しているため、温度差が少なく湿気も溜まりにくい状態です。そのため、ダクト内や風道にホコリが溜まりにくく結露も発生しにくいシステムと言えます。
小屋裏・床下・階間:空調設備の他にフィルターがないため、細めに掃除をしないとダクトや風道にホコリが溜まりやすくなります。また、ダクトを利用したシステムでは、小屋裏や床下などの空気循環が不十分な場合もあり、温度差が生じやすく湿気も溜まりやすいため、結露が生じやすい環境になっています。
結露
結露は、カビを発生させてしまう大きな原因の一つです。結露は、温度差と湿度が大きく関係しており、空気が冷やされることで起こります。
夏の場合:ダクトの内外部や風道は高湿高温になっています。そこに冷たい風が流れるとダクト内や風道の空気が急激に冷やされ、ダクト内外や空調設備周辺で温度差が生じ結露が起こりやすくなります。また、冷たい空気と部屋の空気が混ざる通気口周辺では、温度差が大きく結露が発生しやすい場所になります。
冬の場合:冬は室内と外気の温度差が大きくなります。断熱性能が高くでも気密性が低いと外の冷たい空気が室内に入り込むため、室内の空気が急激に冷やされ結露を起こす可能性があります。特に、暖房時の温風は高熱となっているため、急激に冷やされると簡単に結露してしまうこともあります。
エアコンのように冷風や温風をそのまま各部屋に届けるのではなく、室内の空気を取り入れ、室内の温度に近づけてから空気を送ることで温度差を抑えることができ、結露防止に繋がります。空調室や空調箱があるシステムではこのようなタイプが多いです。
リスクの低いシステムとは
結露やカビの発生とホコリが溜まるリスクを抑えるシステムは、空調室(空調箱)の中に空調設備があり、強い冷風や温風を出さず、ダクトや風道の空気循環が常に行われるシステムです。このようなシステムを選ぶことで、ホコリが溜まらず結露防止に繋がり、カビも抑制することでメンテナンス費用やリスクを抑えることができます。