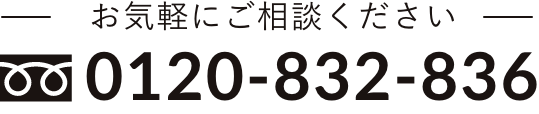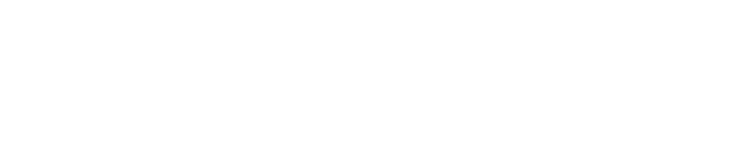【2025年最新】窓の断熱で光熱費を削減!効果的な方法・費用・補助金まで徹底解説
目次
窓と断熱の関係は?
窓と断熱の関係は、快適に暮らす上で重要な要素の一つで光熱費にも大きく影響するものです。断熱性の高い住宅をつくるうえで、最も見落とされがちでありながら重要なのが窓です。寒冷地や夏の猛暑を想定した住宅では、屋根や壁の断熱と同じくらい窓の断熱対策が室内環境の快適性を大きく左右します。
家の断熱性の半分以上は「窓」で決まる
住宅の断熱性において、最も大きな熱の出入り口となるのが窓や玄関などの開口部です。夏場に室内に入る熱の約60~70%、冬場に室内から逃げる熱の約50〜60%が窓からであるとされています。これは、壁や天井、床の断熱性能がいくら高くても、窓の性能が低ければほとんど熱は出入りしてしまうことを意味しています。
特に古い住宅などアルミサッシ+単板ガラスの窓が使われている場合、その断熱性能は非常に低く、外の寒さや暑さがほとんど伝わってきます。そのため、住宅全体の断熱性能を高めたいのであれば、まず最初に取り組むべきなのが「窓の断熱」なのです。
熱の出入りはどこから?外気侵入のメカニズム
断熱の基本は字のごとく熱を断つ(熱を移動させない)ことです。熱の移動は、主に放射熱(輻射熱)、伝導熱、対流熱の3つあり、温度差があると高い方から低い方へと移動します。冬場は室内の熱が外に逃げ、夏場は外の熱気が室内に入ってくるため、これらの熱移動を防ぐことが重要になります。
・放射(輻射)熱:物質を通さずに伝わる。(例.太陽光や焚火の熱)
・伝導熱:外(内)の熱が物質内で移動し内(外)に伝わる。(例.フライパンの底を加熱すると表面も熱くなる)
・対流熱:空気や液体などが移動し熱が伝わる。(例.お風呂のお湯(上の方が熱く下の方が冷たい))
断熱性の高い窓は、放射・伝導・対流をなるべく防ぐことで、熱の移動を防いでいます。
知っているようで知らない窓の用語
二重窓
二重窓とは、既存の窓の内側にもう一つ窓を取り付け、窓を二重構造にすることです。窓を二重構造にすることで、断熱性、防音性、防犯性、室内の結露対策などの効果が期待できます。内窓、二重サッシ、インナーサッシと呼ばれることもあります。ペアガラスとは異なり、窓枠が2枚あります。
ペアガラス・複層ガラス・トリプルガラス
複層ガラスとは、複数のガラスの間にガスや空気を入れた中空層を設けたガラスです。トリプルガラスは、3枚のガラスを使用した複層ガラスです。ペアガラスは、2枚のガラスの間に中空層を設けた複層ガラスの一種ですが、AGC株式会社の登録商標です。一般的には、複層ガラスは2枚、トリプルガラスは3枚ガラスを使用しているイメージです。
Low-Eガラス
Low-Eガラスとは、ガラスの表面に特殊な金属膜をコーティングしたガラスです。Low-EはLow Emissivityの略で低放射を意味します。主に複層ガラスにコーティングされ、日射遮蔽型と日射取得型があり、室内への熱の流入を防ぐ場合は日射遮蔽型、室内への熱の流入を増やす場合は日射取得型が使用されています。
樹脂サッシ・アルミサッシ
サッシとは、窓枠に使われる建材です。樹脂サッシは、樹脂でできた窓枠で断熱性に優れていますが、耐候性(雨風や紫外線に対する耐性)はアルミサッシと比べやや劣ります。アルミサッシは、アルミでできた窓枠で、耐候性に優れている一方、樹脂サッシと比べて断熱性では劣ります。
他にも、アルミと樹脂を組み合わせたアルミ樹脂複合サッシも存在し、主に本州で多く採用されています。また、木製サッシも存在し、熱伝導率が低いため断熱性に優れていますが、塗装などメンテナンスが必要なため、樹脂かアルミサッシのどちらかが使用されることが多いです。
窓の断熱性を高める方法
窓の断熱性を高める方法は、主に内窓の設置とサッシやガラスの交換です。窓の断熱状況や予算に合わせて、適切な方法を選ぶと良いでしょう。また、緩衝材やプラスチック段ボール、断熱カーテンを利用するなど簡易的で安価な方法でも窓の断熱性を高めることが可能です。
内窓(二重窓)
内窓の設置は、既存の窓(外窓)の内側にもう一つ窓(内窓)を取り付け、窓を二重構造にすることです。内窓のメリットは、断熱性が向上し防音効果もあることです。デメリットは、二重窓の設置ができない場合があり、さらに外窓と内窓の間で結露を起こす可能性があることです。
特に寒冷地や古い住宅では、既存のサッシをそのまま活かせる手軽な断熱強化手段として非常に人気があります。一方で、外窓のタイプによって内窓を設置出来ない場合がある点には注意が必要です。
樹脂サッシ
樹脂サッシとアルミサッシでは、樹脂サッシの方が断熱性に優れています。樹脂サッシにすることで、断熱性を高めるだけではなく結露もしにくくなるため、カビの発生予防にも繋がります。但し、ガラスも複層ガラスなど高断熱なもので組み合わせなければ、効果は不十分になる可能性があります。
Low-E複層ガラス
Low-E複層ガラスは、特殊金属膜と2枚以上のガラスに中空層を設けた断熱性が非常に高いガラスです。Low-E複層ガラスに樹脂サッシを組み合わせた窓は、北海道で採用率が高いほど断熱性の高い組み合わせです。特に、トリプルガラスと樹脂サッシの組み合わせは高い断熱効果をもたらします。
DIYでできる断熱
プチプチ(気泡緩衝材)やプラスチック段ボール、断熱シート(アルミ系)を利用することで断熱効果を上げることもできます。プチプチやプラスチック段ボールは室内の熱を外に逃さず、断熱シート(アルミ系)は夏の放射熱に効果があります。但し、いずれも効果は限定的であるため、サッシと比べ大きく断熱性が向上することはなく、適切に設置しなければ効果が薄い上、結露を起こすなどデメリットもあるため使用には注意が必要です。
また、断熱カーテンを使用することで一定の断熱効果を得ることも可能です。断熱カーテンは、外からの熱の影響を受けにくく、室内の熱を逃しにくい効果があります。但し、カーテンを閉めなくては効果を発揮しないため、日中でカーテンを開けている状況では、あまり効果を感じることはできません。
窓断熱による変化
窓断熱による変化は、冷暖房費削減、住宅・設備の寿命延長、健康リスクの低減です。窓断熱によって冷暖房の運転時間が減少し光熱費削減と設備の寿命延長に繋がります。また、温度差が抑えられることでヒートショックなどの健康リスクを低減し、温度差による結露防止に繋がり住宅の劣化防止に繋がります。
窓断熱で冷暖房費はどれくらい安くなる?
窓断熱で冷暖房費は、年間で数万円安くなります。窓の断熱化による冷暖房費の削減効果は、住宅の構造や地域の気候条件、従前の窓や枚数によって異なりますが、一般的には年間で10〜30%程度の冷暖房費を削減できると言われています。冬の寒冷地などエネルギー消費が多い地域や窓の枚数が多いほど効果は大きくなります。
断熱リフォームの初期費用と回収年数
断熱窓リフォームの初期費用は、1枚あたり窓の交換で10~50万円、内窓設置が10~30万円が目安です。窓の種類や大きさ、工法によって異なります。初期費用としてある程度の出費が必要ですが、光熱費の削減と補助金制度の活用によって10年前後で回収できるケースが多いですが、交換枚数が多いほど回収年数は長くなります。
窓の交換には、既存の窓やサッシの上に新しくサッシをかぶせる「カバー工法」と窓枠ごと交換する「はつり工法」があります。カバー工法の方が安価で工期も短く済みますが、窓のサイズが小さくなります。はつり工法は窓のサイズを維持できますが、外壁補修が必要となりリフォーム費用が高額になります。
ランニングコストの視点で見る断熱投資の価値
ランニングコストの視点で見る断熱投資の価値は、光熱費を削減するだけではなく住宅や設備の寿命と健康への影響です。冷暖房機器の稼働時間や設定温度を抑えることで、設備の寿命が延びる可能性があります。また、温度差を抑えることでヒートショックなどの健康リスクを低減し、さらに結露を抑制し建物の劣化防止に繋がります。
新築・リフォーム時の断熱窓の選び方
注文住宅で選ぶべき断熱性能の高い窓とは
注文住宅で選ぶべき断熱性能の高い窓とは、北海道などの寒冷地で樹脂サッシとダブルLow-Eトリプルガラスの組み合わせ、東京などではアルミ樹脂複合サッシとLow-E複層ガラスです。この組み合わせは、現行のZEH水準の断熱性の例として国土交通省の資料に掲載されています。
2025年から住宅の断熱基準が変わり、従来の省エネ基準の断熱性を新築住宅に義務付けることになりました。また、2030年までには現行のZEH水準の断熱性を新築住宅に義務付ける予定となっています。2030年における最低基準であることを考えると、最低限必要と考える方が良いでしょう。
リフォーム時の断熱窓の選び方
リフォーム時の断熱窓の選び方は、予算と可能な施工方法から選択肢を絞り決める方法です。例えば、マンションの窓交換等は制限されていることがあり、内窓の設置に限られるケースがあります。また、戸建住宅で窓の交換のみを予定していても、施工方法によって外壁補修まで必要になり予算オーバーとなるケースもあります。
まずは可能な施工方法を明らかにし、予算内で断熱窓リフォームができるように考えることが重要です。その上で、大きい窓があるリビング、温度差が激しい廊下や洗面、お風呂など優先順位をつけながら選んでいきます。
補助金の対象製品から選ぶ
窓の交換や内窓設置等については、省エネリフォームとしてこの数年補助事業が行われています。国や各自治体などで行われており、要件は異なりますが一定の窓の断熱改修をすることで補助金を受け取ることができるため、対象製品から選ぶことでお得に窓断熱ができる可能性があります。
補助金・助成金でお得に断熱リフォーム
【2025年版】先進的窓リノベ事業の最新情報
「先進的窓リノベ事業」は、2023〜2024年に実施された人気の補助制度で、2025年も継続・拡充されています。この制度の大きな特徴は、高断熱窓への交換に対して最大200万円の補助が受けられる点です。
主なポイントは以下の通りです:
対象:既存住宅(戸建て・マンション問わず)
工事内容:高性能な断熱窓への交換(内窓・外窓・ガラス交換)
補助額:窓のサイズや性能に応じて、1箇所あたり数千〜数万円
条件:省エネ性能の証明(製品仕様書など)と申請が必要
補助金の申請は、登録事業者のみ行うことができ、工事の発注者は身分証明書や必要書類の記入などを行う程度ですので、登録事業者と相談の上いくら補助金が受け取れるか確認しておきましょう。
注意点としては、
・予算と期限があること
・申請手数料が必要な業者がいること
・工事前後の写真が必須であること
上記が挙げられます。また、最近では実際に取り付け予定のない窓などを事業者が申請し補助金を受け取ろうとするケースがあるため、契約書の内容と補助事業の事務局から送付される補助金の決定通知書等を確認し、問題ないか必ず確認しておきましょう。
よくある質問
窓に貼る断熱シートは本当に効果がありますか?
窓に貼る断熱シートは、一定の効果がありますが性能は限定的です。断熱シートは主に窓からの放射熱の出入りを緩和する目的で使われ、冬場には外気からの冷気を遮断し、夏場には直射日光の熱を抑える効果が期待できます。但し、放射熱ではない対流熱や伝導熱の対策にはならない点には注意が必要です。
窓リノベ補助金(2025年版)はいつから申請できますか?
2025年版「先進的窓リノベ事業」は、既に申請可能な状態です。予算や期限が決まっているため、早めに検討することをおすすめします。特に、他のリフォームと合わせて行う予定で確認申請が必要な場合、確認済証の発行まで時間を要しているため、早めにリフォーム会社に相談すると良いでしょう。
窓にプチプチを貼ると断熱に効果的ですか?
窓にプチプチ(気泡緩衝材)を貼ると、断熱に一定の効果をもたらします。主に冬季に使用され、窓からの冷気の侵入をやわらげ、室内の暖かさをある程度保つことができます。但し、見た目が生活感に溢れるため人目につく窓やリビングには不向きであると言えます。
窓の断熱シートは何年くらい持ちますか?
市販されている断熱シートの耐用年数は、約1年〜3年程度が目安です。特に夏の直射日光や結露による湿気の影響を受けやすく、剥がれや変色、カビなどが発生する可能性もあるため、定期的なメンテナンスや貼り替えを前提に考えておくとよいでしょう。
内窓と外窓、どちらが断熱効果が高いですか?
元々の外窓と内窓の性能によるため一概には言えませんが、内窓+既存窓の組み合わせが高いとされています。これは空気層が二重になり、熱の移動を効果的に抑える「複層構造」になるためです。一方、外窓でも樹脂サッシ+ダブルLow-Eトリプルガラスの組み合わせの方が断熱効果が高くなる場合もあります。
断熱性能の高い窓にすると結露も防げますか?
断熱性能の高い窓にしても、結露を防ぐことはできません。結露は、温度差と湿度の関係から発生するため、湿度が高すぎると少しの温度差でも結露が発生します。完全に防ぐことはできなくても、断熱性能の高い窓にすることで温度差を抑えることができるという点で、結露対策として非常に有効です。