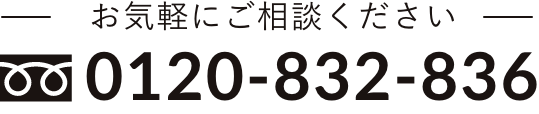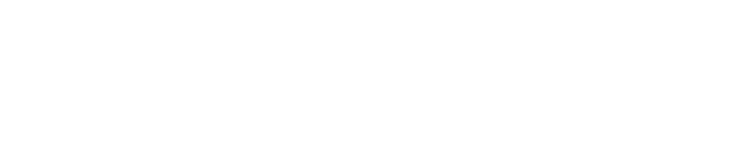【北海道の人は必見】電気・ガス・灯油どれが安い論争に終止符!
目次
電気・ガス・灯油どれが安い?
電気・ガス・灯油では、電気の方が安い、または近い将来安くなります。世界中で行われている脱炭素社会に向けた取り組みと、日本のエネルギー安全保障に向けた取り組みにおいて、電化と非化石転換が非常に重要であると位置づけられているからです。そのため、電気は今後ガスや灯油と比較して安く利用できる可能性が高いと言えます。
電気・ガス・灯油の基本を知ろう
電気とガス・灯油は、家庭や職場などあらゆる場所で使用するエネルギー供給の主な選択肢です。それぞれに異なる特徴があり、コストや使い勝手にも違いがあります。ここでは、電気・ガス・灯油の基本的な仕組みや料金体系について詳しく解説します。
電気とは?特徴と仕組み
電気とは、電子(電荷)が移動する現象で、エネルギーそのものを指します。電子は物質や原子などのまわりにあるため、他のエネルギーから電気エネルギーに変換しやすく、また電気エネルギーは他のエネルギーに変換が簡単で扱いやすいことから、様々なところで使用されています。
電気は、発電所で作られたエネルギーを送電線を通じて供給されており、日本では主に以下の発電方法が利用されています。
- 火力発電(石炭・天然ガス・石油):安定供給が可能だが、CO₂排出量が多い。
- 水力発電:再生可能エネルギーの一つで、安定した供給が可能。
- 太陽光発電・風力発電:クリーンエネルギーだが、天候に左右される。
- 原子力発電:CO₂排出が少なく大量供給が可能だが、安全性への懸念がある。
電気は主に照明・冷暖房・給湯・調理など幅広い用途に利用されます。特にオール電化住宅では、エコキュートやIHクッキングヒーターが導入されることが多く、ガスを使わない生活が可能になります。
また、近年ではヒートポンプ(空気中の熱を移動させる)技術を用いたエコキュート(給湯器)や冷暖房設備(エアコンなど)を導入した「スマート電化」が注目されており、従来のオール電化に比べて大幅に電気代を削減できるようになっています。
ガスとは?種類と使い方
ガスには主に、都市ガスとプロパンガス(LPガス)の2種類があります。
- 都市ガス:メタンを主成分とする天然ガス。ガス管を通じて供給されるため、ガス会社と契約すれば使用可能。
- プロパンガス(LPガス):プロパンやブタンを主成分とし、ガスボンベで供給される。都市ガスが通っていない地域で主に利用される。
都市ガスは、天然ガスを主原料としており、プロパンガスは原油や天然ガスが主原料となっています。資源エネルギー庁によると、天然ガスの海外依存度は97.8%と、そのほとんどを海外からの輸入に頼っています。
ガスは主に調理・給湯・暖房に使用されます。特にガスコンロやガスファンヒーターは即時加熱が可能で、調理や暖房の効率が高いのが特徴です。また、ガス給湯器は電気温水器と比べて短時間でお湯を作ることができます。
灯油とは?種類と使い方
灯油は、原油を蒸留し得られる粗灯油から精製しています。原油からは他にも、ガソリンになるガソリン・ナフサ、プロパンガスになるLPガスなどがあります。灯油は主に給湯・暖房に使用されます。
電気・ガス・灯油の料金体系の違い
電気とガスでは、料金体系が大きく異なります。
電気料金
・基本料金(契約アンペアなどに応じて決まる)
・電気量料金(使用量に応じて変動する)
・燃料調整費(発電コストの変動による調整分)
・再エネ賦課金(再生可能エネルギーの普及のための追加料金)
電気料金では、従量電灯(電気の使用量に応じて料金を支払う電気料金プラン)とオール電化住宅などがお得に使える料金プランの大きく2つがあります。その他、燃料費調整が毎月行われ、再エネ賦課金は毎年定められた金額を使用量1kWhあたり支払うものです。
都市ガス料金
・基本料金(契約しているガスの種類や使用機器により決まる)
・使用量料金(使用量に応じて変動する)
・原料費調整額(輸入価格などの影響で変動する)
ガス料金も、基本料金と使用量、さらに原料価格によって毎月調整された上で料金が決定します。ガスの場合、エコジョーズやコージェネレーション設備など、住宅で採用している暖房・給湯設備に応じて様々な料金プランがあります。
プロパンガス料金
・基本料金(契約しているガスの種類や使用機器により決まる)
・使用量料金(使用量に応じて変動する)
・原料費調整額(輸入価格などの影響で変動する)
・設備費の上乗せ(今年から禁止)
プロパンガス料金も、基本料金と使用量、さらに原料価格によって毎月調整された上で料金が決定します。プロパンガスが高いと言われている理由の一つに、設備費がありました。エアコンやインターフォンなどをガス会社が無料貸与する名目で賃貸などに設置し、設備費をガス料金に含めて利用者に請求していたことが高い理由の一つでしたが、新規契約や契約更新する賃貸でも今年から禁止になります。但し、ガスに必要な設備については明示することで請求できます。
灯油料金
・配達量料金(配達された灯油の量に応じて変動する)
灯油の場合、基本的に配達された分の料金を支払うことになり、依頼する会社で大きく料金が異なります。定期配達を依頼することで単価料金を下げられることが一つの特徴です。
現在の各料金は、電気では石炭・原油・LNG(液化天然ガス)、都市ガスはLNG、プロパンガスはLNGと原油、灯油は原油の輸入価格に大きく影響を受けています。石炭は安値で安定していますが、LNGはウクライナ情勢、原油はOPECプラスによる原油の減産計画で高値と不安定な状況が続いています。
各料金に影響を与える今後の動き
電気・ガス・灯油の価格は、脱炭素社会に対する世界の動きと日本の政策が大きく影響します。電気やガス、灯油は二次エネルギーで、石油・石炭・天然ガスなどの一次エネルギーから作られます。日本では、一次エネルギーのうち約85%を輸入に頼っており、エネルギーの安定供給と確保、さらに脱炭素化を目指し今後大きな転換期を迎えます。
脱炭素化が止まらない理由
世界中で行われている脱炭素化への取り組みは単なるビジネスの話ではなく、2015年に世界150以上の全ての国と地域で合意された「パリ協定」の国際的な枠組みによるものです。パリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2℃より低く抑え、1.5℃に抑えることを目指し、温室効果ガスの削減に取り組むとしています。
気温が上昇すると、気候変動だけではなく、干ばつや洪水、水や食料不足、感染症の拡大、動植物の絶滅など大きな影響を与えます。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)では、2023年3月に「温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地がない。」と、以前とは異なり事実として記述しています。
最近では、アメリカがパリ協定からの離脱を表明(2026年1月離脱予定)しました。以前のトランプ政権時にも離脱しましたが、バイデン政権ですぐに復帰しています。また、前回も今回もアメリカに続いて離脱を表明している国はなく、脱炭素化に向けた取り組みが止まるとは見られていません。
日本のエネルギー安全保障が急務
エネルギー安全保障とは、国民生活や社会経済活動において必要なエネルギーを妥当な価格で安定的に確保・供給することです。エネルギー自給率が約15%と大半を輸入に頼る日本にとって、昨今のウクライナ情勢のような出来事があると電気やガス、灯油の値上がりに直結し、生活や経済活動に大きな影響が出ます。
そのため、日本では脱炭素化を進めるのと同時にエネルギー自給率を上げる必要があるため、石油や天然ガスなどの化石燃料に頼らないエネルギーの確保を目指し、様々な技術開発や政策を実施・予定しています。
具体的な動き
2026年から「排出量取引制度」、2028年から「化石燃料賦課金」が始まる予定です。
排出量取引制度とは、一定以上の二酸化炭素を排出する企業に参加が義務付けられるもので、各企業ごとに排出量の上限が定められ、排出枠の売買が可能になります。排出量の上限を超過した企業は排出枠を購入し、削減した企業は枠を売却できるため、脱炭素化を行うほど企業にとってプラスになることが予想されます。
化石燃料賦課金とは、化石燃料(石油や天然ガスなど)の採取や輸入事業者に対して、CO2排出量に応じて賦課金が課せられるものです。当然ながら、電気・ガス・灯油を使用する家庭でも使用料金にプラスされると考えられ、特にガスと灯油の利用者にとって負担となることが考えられます。
電気・ガス・灯油は今後どうなる?
電気・ガス・灯油が今後どうなるか、多くのことが「エネルギー基本計画」に記載されています。エネルギー基本計画では、2040年、そしてその先に向けた今後の課題や方向性などを取りまとめています。
都市ガス
・基本的な方向性
都市ガスの原料となる天然ガスは、再生可能エネルギーによる発電、石炭火力発電からの脱却に際し重要な役割を持つとしています。一方、家庭で使用する都市ガスはLNG(液化天然ガス) の主成分と同じメタンである合成メタン及びバイオメタンと、メタン以外のガス体エネルギーである水素への転換が考えられています。
・合成メタン
合成メタンはCO2と水素から合成され、既存のガス管や設備が使用できると考えられていることから設備交換の費用負担がなくて済むと考えられます。一方、CO2の回収コスト、合成するための設備コスト、そして最もコストが掛かるとされている水素の製造があります。現在の価格程度で提供できるほどの製造・供給の見通しが立っておらず、引き続き技術開発に取り組むとしており、賦課金や排出量取引制度の影響を大きく受けると思われます。
・2030年から更なる負担も
2026年から排出量取引、2028年から賦課金が始まりますが、2030年度から合成メタンを含めガスの5%をカーボンニュートラル化していくとしています。ガスの一般的な調達費よりも割高になる部分は、託送料金原価に含めることができる仕組みを構築するとしており、さらにガス利用者の負担が増加する可能性があります。
プロパンガス
・基本的な方向性
プロパンガスは、約4割の家庭に供給され備蓄体制も整備されており、貯蔵が簡単で劣化のない分散型エネルギーとして位置付けられています。プロパンガスは、原油や天然ガスを主原料としているため、カーボンニュートラルの達成のために2050年には国内のプロパンガスをグリーンLPガス(化石燃料に頼らないLPガス)に代替していきます。
・バイオLPガス
バイオLPガスはプロパンガスの代替えとして期待されているものです。バイオディーゼル(廃食用油や植物油を原料とする燃料)とともに副生されますが、大量生産に課題があり、世界的にみても先進的技術が確立されていません。そのため、賦課金等の影響を長く大きく受ける可能性があります。
・配達料金
人工減少、少子高齢化などの影響により、LPガスの配達コストが増加する可能性があります。特に、都市部以外では人口が少なく居住場所がばらつく可能性が高く、配達の手数料が高額になる可能性もあります。
灯油
・基本的な方向性
石油業界では、革新的な脱炭素技術の研究開発と社会実装にも積極的に取り組むとしていますが、主にガソリンや軽油など、自動車や航空、船舶などに関する方向性に関する記述がほとんどであり、灯油に関しては合成燃料への転換が可能性として考えられます。
・不透明なことが多い
灯油のカーボンニュートラル化がどのような方向に向かうか不透明な状況です。一部、灯油の代替として利用できる合成燃料の開発が行われているようですが、ガスの代替と同様にCO2の回収と水素製造が必要なため、現在のような価格で提供できるかはわかりません。
電気
・基本的な方向性
電気は、2040年度までに太陽光発電などの再エネ発電を4~5割程度(現状22.9%)、原子力を2割(現状8.5%)、火力を3~4割程度(現状68.6%)にすることを見通しており、さらに国民負担の抑制を図るため、再生可能エネルギーのコストを競争力ある水準に低減させ、自立的に導入が進む状態を早期に実現していくとしています。
・火力発電が減る
排出量取引や賦課金では、化石燃料を使用すると費用負担が増大しますが、火力発電の割合を減少させることで負担の軽減に繋がります。特に、二酸化炭素の排出量の多い石炭火力をフェードアウトしていくとしており、排出量が比較的少ないLNG(液化天然ガス)火力にシフトし、電力供給の安定化を図りつつ将来的に水素等の活用により脱炭素化も可能であるとしています。電気の場合、着実に脱化石燃料に向けた道筋が見えており、さらに水素やアンモニアなど新しい技術による発電も研究されていることから、費用負担が増加するよりも減少する可能性の方が高いと言えます。
・送電設備の負担軽減
電気は、ガスや灯油を使用する家庭においても使用されるため、電力需給に関わる設備や送電線などの整備等の費用について、一人当たりの負担が軽減されます。また、再生可能エネルギー電源の立地地域の負担とその全国への裨益を踏まえ、エリアを越えた費用負担の仕組みも検討していくとしており、地域差による負担差も少なくある可能性もあります。
引用:エネルギー基本計画、都市ガスのカーボンニュートラル化について、エネルギーを起点とした産業のGX(グリーントランスフォーメーション)について、石油業界のカーボンニュートラル行動計画
これらの動きはGX(グリーントランスフォーメーション)と呼ばれ、化石燃料を使わずクリーンエネルギーを活用していくための変革や実現に向けた活動のことを指します。2025年から新たにGX志向型住宅という省エネ住宅の区分が創設され、今後益々エネルギー転換に向けた動きが活性化していくことでしょう。
電気・ガス・灯油、選ぶならどれ?
電気・ガス・灯油から選ぶなら、電気が間違いなく良いでしょう。日本のエネルギー安全保障対策、脱炭素社会に向けた世界的な取り組み、今後の見通しなどを考えると、電気ほど安心できるものは現状ないと言えます。
住宅を建築、購入する人は30年、40年と長い間住宅ローンを組む人も多いですが、その間にガスや灯油、電気の利用料金は大きく変わっていくことが予想されます。初期投資が安いガスや灯油の設備を選んでも、早ければ2026年から少しずつ負担が増える可能性があります。
上記は2040年、遅くとも2050年までのエネルギー転換の話なので、住宅ローンを完済するまでにエネルギーや光熱費を取り巻く環境は大きく変わってしまうということです。後悔しないためにも、長い目で判断していくことが重要になります。
オール電化の電気料金が高い場合
オール電化で電気料金が高い理由は、主に「ヒートポンプ機器を利用していない」「料金プランが適切ではない」「住宅性能が低い(低下している)」が考えられます。設置している設備を交換する、料金プランを変更する、省エネ改修を行うなどで電気料金を下げることは十分可能です。
ヒートポンプ機器とは、空気中にある熱を集めて給湯や冷暖房を行うもので、エコキュートやエアコンが代表的な設備です。家の冷暖房をエアコンに変える、給湯器をエコキュートに変えるだけでも大きく消費電力を下げることができます。
また、住宅性能については、断熱欠損がある、気密性が低いなども考えられますが、大きいのは窓と玄関ドアです。窓などの開口部からの熱の損失は約50~70%と非常に大きく、窓や玄関ドアを交換するだけでも大きな効果があります。
この数年間、住宅省エネキャンペーンを行っており、住宅の省エネ改修や省エネ設備への変更に補助金が出ます。今年は住宅省エネ2025キャンペーンが行われますので、これを機にリフォームを考えるのも良いかもしれませんね!