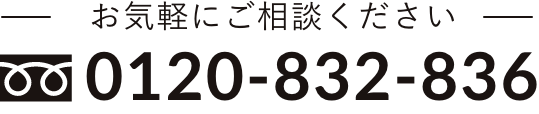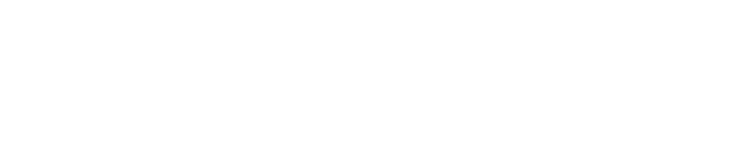全館空調は1階と2階で温度差が出る?原因や対策を徹底解説!
目次
1.全館空調とは
全館空調とは、家全体の温度を一括して管理する空調システムです。リビングや寝室だけでなく、廊下・洗面所・トイレなども含め、すべての空間をほぼ同じ温度に保つことで、季節を問わず快適な住環境を実現します。一般的に1~2台の空調設備からダクトや風道を通して各部屋に風を送る方法で、温度のムラが少ないことが特徴です。
全館空調の基本的な仕組み
全館空調の基本的な仕組みは、天井裏や床下、専用スペースに設置された空調ユニットからダクト配管や風道を通じて、家中に温風・冷風を送ることです。主な種類として、温風・冷風を各部屋に送り込む対流式(送風式・循環式)と対流式に床暖房のような輻射熱の効果を合わせた複合式があります。
送風式:ダクトやファンを利用して、確実に温風と冷風を各スペースに送り込む方法です。
循環式:温度差により空気が移動する性質を利用して、各スペースに温風と冷風を自然に送り込む方法です。
複合式:各スペースだけではなく床下や天井裏などにも温風と冷風を送り、床や天井も冷暖房する方法です。
選ぶ方式によって温度調整の自由度や電気代、快適性が変わるため、導入前にしっかりと特徴を把握しておく必要があります。
個別エアコンとの違いとは?
全館空調と個別エアコンとの違いは、空調管理の範囲と一体性です。個別エアコンは部屋ごとに設置され、それぞれの室温を個別にコントロールするため、空調範囲が異なり温度差が出やすくなります。一方、全館空調は家全体を一つの空間として捉え、同じ温度帯で管理するため、部屋間の温度差よる不快感がありません。
また、全館空調は家全体の空気が常に循環されるため、湿度対策や空気清浄機能にも期待ができます。但し、個別エアコンに比べて初期費用が高く、メンテナンスには専門知識が必要である点は留意すべきポイントです。
2.1階と2階で温度差は出る?全館空調のリアルな実態
全館空調は、1階と2階で温度差が出る場合があります。基本的に1階と2階で大きな温度差にならないように設計されていますが、外気温や間取り等の影響で1~3℃くらい温度差が生じる場合があります。それとは別に、住宅性能やシステム設計、導入する地域によってそれ以上に温度差が生じてしまう場合があります。
暖気と冷気の性質が引き起こす温度ムラ
空気には「暖かい空気は上に、冷たい空気は下に移動する」という性質があり、これが1階と2階の温度差に大きく影響します。例えば、夏場の冷房は床付近の空気が冷えやすく、1階が比較的涼しくなりやすいです。一方で、冷気が上まで届きにくいため、2階が暑く感じることがあります。逆に冬場は暖房で温められた空気が上に移動し、2階が暖かくなり1階が寒いという状況になりやすいのです。
よくある悩み「1階が寒くて2階が暑い」は本当か?
全館空調で1階が寒くて2階が暑いということはあり得ます。冬の暖房の空気が1階に行き渡らずに2階に移動してしまう場合や、夏の冷房の空気が1階に溜まり2階に行き渡らないなどが考えられます。これによる温度差で1階が寒く2階が暑くなる場合があります。
よくある悩み「1階が暑くて2階が寒い」は本当か?
全館空調で1階が暑くて2階が寒いというのはあまり聞きません。但し、1階が暖かく2階が寒いという可能性はあり得ます。これは、本来2階まで暖めるために強い温風が必要な場合で、1階を快適な温度に設定した結果2階の暖房が不十分である場合です。
3.全館空調でも1階と2階で温度差が出る理由とは?
全館空調でも1階と2階で温度差が出る理由は、冷暖房の風量、システム設計、気密・断熱性能が原因です。全館空調であっても1階と2階で多少の温度差が出る場合がありますが、温度差が大きすぎて不快に感じる場合は空調システムの仕組みや住宅の構造に起因することがほとんどです。
送る風量が部屋毎で変わらない
全館空調システムの中には、各部屋へ一定の風量を送るシステム(送風式)があります。この送る冷風や温風の風量を各部屋で均一、もしくは部屋の大きさで簡易的に設定していることがあります。部屋の広さが変わると必要な風量も変わりますが、風量が一定の場合は冷房や暖房が効きすぎてします場合があります。
例えば、20畳のリビングを冷房する場合と、6畳の部屋を冷房する場合で必要な風量は異なります。仮に20畳のリビングに必要な冷風を6畳の部屋に送ってしまうと6畳の部屋が過剰に冷えてしまいます。このように、送る風量が部屋毎で考慮されていないと温度差が生じてしまいます。
必要な冷風・温風が届いていない
全館空調システムの中には、温度差による空気の移動(循環式)を利用したシステムがあります。この場合、暖房は良くても冷房の効果が弱い、反対に冷房は良くても暖房の効果が弱くなる場合があります。また、ダクトや風道の設計によって必要な冷気・暖気が届かないことがあります。
例えば、床下に空調設備を置いた場合、温かい空気は上にいくため1階・2階共に暖房効果が見込める一方、冷たい空気は下に行くため2階の冷房効果が弱くなることがあります。また、ダクトや風道が空調設備から遠いほど必要な風量が届きにくいことも影響してきます。
気密性や断熱性能が低い
住宅の気密・断熱性能が低いと、せっかく全館空調で調整された冷気や暖気が外へ逃げてしまい、階によって温度差が発生します。特に床下や屋根、開口部からの熱の出入りが大きい住宅では、1階の冷え込みや2階の熱こもりが顕著になります。
4.施工前に1階と2階の温度差を抑える5つの対策
全館空調の性能を最大限に引き出すためには、施工前の設計段階で上下階の温度差を意識した対策を講じることが重要です。後からの修正は難しいため、施工前のシステム選びの段階から温度差を最小限に抑える対策が重要です。
システム選びを工夫する
全館空調で最も適したシステム選びは、間取りごとに空調負荷が計算されているシステムを選ぶことです。空調負荷とは、温度や湿度を一定に保つために必要な熱量のことを指し、冷房負荷や暖房負荷と呼ばれます。空調負荷を間取りごとに計算した上でダクト配置等を行うシステムであれば、温度差を最小限に抑えることができます。
吹き出し口の位置を工夫する
全館空調には、風を送るダクトや風道の他に、風を出すための吹き出し口が存在ます。一般的に、冷房を重視するシステムや地域の場合は吹き出し口が上側(天井もしくは天井近くの壁)に付いていることが多く、暖房を重視するシステムや寒冷地などの場合は床に付いていることがほとんどです。
例えば、暖房を重視する北海道で、吹きだし口が上側についていても温かい空気は下まで行き渡らない可能性があり、足元が冷えてしまいます。このように、システムだけでなく、使用する地域によって吹き出し口を意識しておくことが重要です。
気密・断熱性能を確保する
どれだけ良い空調システムを導入しても、家そのものの断熱性・気密性が低ければ意味がありません。断熱材の施工精度やサッシの性能、気密シートの貼り方など、基本性能をおろそかにしないことが鉄則です。
全館空調の多くは、断熱性能でZEH水準以上(断熱等級5以上)、気密性能であるC値は1.0㎠/㎡以下としているところが多いですが、より良い冷暖房効果と光熱費削減を目指すのであれば断熱等級6以上、C値は0.5㎠/㎡以下を目指すことも良いでしょう。
また、設計上だけではなく、第三者評価による現場検査を行うことでより安心できます。住宅性能に関する現場検査は建設性能評価、気密に関する検査は気密測定があります。これらの検査を標準としていない住宅会社は多いため、打ち合わせの時点で検査・測定が可能か否かを確認しておくことが重要です。
補助設備を検討する
本来であれば気温差が生じないシステムを選ぶ必要がありますが、予算等の関係で別のシステムを選ぶことが困難な場合もあります。その場合、効果が弱いと思われる部分に対する補助エアコンやシーリングファンなどの補助設備を併用することも効果的です。
但し、追加の設備費用やメンテナンス面なども考慮した上で適したシステムと比較した方が良いでしょう。
上下階の温度差を意識した間取りの工夫
熱負荷を計算したシステムの場合、間取りによる温度差、少なくとも暑い・寒いという不快感への影響はほとんどありません。もし熱負荷を計算したシステムを選べない場合、吹き抜けをなくすなど間取りの工夫が必要になります。
5.施工後に1階と2階の温度差を抑える5つの対策
施工後に「1階が寒い」「2階が暑い」といった温度差に気づくケースは少なくありません。一方で、完成後に空調システムを変更することは難しく、出来る対策は限られています。但し、諦める必要はなく、適切な対策を講じれば快適な住環境を取り戻すことが可能です。
ダクトの配置とダクト交換
ダクトの長さや分岐の位置が原因で、空気が一部の部屋にうまく届いていないケースはあります。この場合、ダクトの再配置や交換によって風量バランスを調整することで、上下階の温度差を改善できる可能性があります。また、断熱ダクトに交換することも効果的な場合があります。
但し、これには空調負荷を計算することやダクト工事が必要なため、費用負担は大きなものになります。
適切な断熱・気密性の確保
1階と2階の温度ムラは、断熱・気密性能が不十分なことでも引き起こされます。特に隙間風や断熱材の劣化が原因となっていることもあります。最近では比較的安い金額のサーモグラフィーが販売されていますので、サーモグラフィーを使用して断熱欠損や大きな隙間がないか調査し、補強や追加工事を行うことも有効的です。
ファンの配置とファン交換
空調設備から各部屋に風を送るために、多くの全館空調ではファンが設置されています。冷暖房効果が弱い部屋に繋がるファンが故障、もしくは送風能力が低下している可能性があります。また、本来必要な風量がファンまで届いていない可能性もありますので、ファンの配置を検討することも良いでしょう。
ファンの交換は、1個あたり数万円で可能な場合が多いため、比較的安価で検討できる方法です。
温度センサーの配置と調整方法
全館空調システムでは、センサーの情報をもとに空調制御が行われるため、センサーの位置が不適切だと正しい制御ができません。空調設備の近く、また冷暖房効果の高い部屋にセンサーがある場合、他の部屋の冷暖房が不十分な状態で空調が制御されてしまうことがあります。温度センターの再配置を検討することも有効かもしれません。
補助設備を導入する
選ぶシステムによって、どうしても冷暖房どちらかの効果が弱いシステムがあります。その場合、補助設備を入れることが最も効果的な方法です。補助エアコンやシーリングファンなどを導入することで温度差をある程度解消できる場合があります。
6.全館空調のある家に住んでいる人の声
全館空調を導入して実際に暮らしてみないとわからないのが「快適性」です。ここでは、実際に全館空調を使って生活している方々の声を紹介します。導入後の感想や、後悔ポイント、施工会社の対応による差など、リアルな体験が参考になります。
1階と2階の快適さに関する実体験
「冬場でも家全体がほんのり暖かく、起きたときに布団から出るのが苦じゃなくなった」「夏は帰宅してもムワッとした暑さがなく快適」という声が多く聞かれます。とくに家全体の温度が均一に快適になるという点は、家族構成が多い家庭や二世帯住宅で好評です。
一方で、「2階が暑くなりすぎる」「1階が冷えにくい」といった階ごとの温度差に悩むケースも一部あります。これは断熱や気密などの住宅性能、システムによる影響が大きく、設計時の工夫や快適な住まいにするシステムの選び方で対処可能です。
導入後に後悔しないためのアドバイス
よく聞かれる後悔の声には、「吹き抜けが思った以上に熱が上に逃げる」「温度センサーの場所をちゃんと考えればよかった」「風の音が気になる部屋がある」といった内容があります。
こうした後悔を防ぐには、事前に施工会社に温度差対策や風量調整について具体的な相談をすることが非常に大切です。また、実際に全館空調を導入した住宅の見学や体験宿泊をするのも有効です。
施工会社の対応で快適性が変わる?
同じシステムを導入していても、「A社では快適だったけど、B社で建てた友人宅は温度ムラがひどい」というように、施工会社の設計力や施工能力によって快適性が大きく異なることがあります。
特に重要なのが、「気密・断熱性能へのこだわり」と「空調と間取り設計の連動性」です。空調機器を売るだけでなく、ダクト経路の検証やゾーニング設計をしっかり行ってくれて、施工中の検査を行える会社を選ぶことが、上下階の温度差を抑える鍵となります。
7.全館空調のメリット・デメリットを比較
階ごとの快適性は本当に保てるのか?
全館空調の最大のメリットは、家全体の温度を一定に保てることです。季節を問わず、家のどこにいても快適な温度に保てるというのは、大きなストレス軽減につながります。特に高断熱・高気密住宅と組み合わせた場合、1階と2階の温度差はほとんど感じないレベルにまで抑えられるケースが多く見られます。
一方で、住宅性能やシステム設計次第では温度差や気流の偏りが生まれることがデメリットとしてあります。そのため、なるべく温度差を生じさせないシステムを選び、設計時で断熱・気密性能を明確にし、現場検査を通じて住宅性能を確保しておくことが重要です。
上下階での不便さを感じる場面はある?
全館空調は基本的に一括制御であるため、部屋ごとの温度調整がしづらいというデメリットがあります。たとえば、「2階よりも人が多いリビングは少し温度を下げたい」といったニーズに対応するのは難しい場合があります。
また、家族によって暑がり・寒がりの違いがあると、ちょっと暑い・寒いと感じる人が分かれてしまうこともあります。そうした場合は、風量や温度調整など使い方で対応する、もしくは衣服で調整する必要があります。
家族全員が快適に過ごすための条件
全館空調で家族全員が快適に過ごすためには、気密性・断熱性の高い家をベースとすることが大前提です。そのうえで、温度差をなるべく生じさせないシステムを選ぶことが効果的です。選ぶシステムによって、補助設備の併用や間取りを工夫しておくことで、ストレスのない快適空間を実現することができます。
8.よくある質問
夏は1階と2階では温度差がありますか?
夏は1階と2階では温度差がある場合があります。冷房時は、冷たい空気が下に溜まりやすく、暖かい空気が上に上がる性質があるため、2階が暑く感じやすい傾向があります。ただし、設計時のダクト設計や風量バランス、温度や風量設定など使用方法の工夫により、温度差を最小限に抑えることは可能です。
一階と二階の温度差を解消する方法は?
一階と二階の温度差を解消する方法は、補助設備の使用や風量調整が安価で効果的です。不快に感じるスペースに対する補助エアコンやシーリングファンなどを利用すること、温度や風量設定を上手く調整する方法があります。但し、断熱や気密性が原因の場合もあるため、サーモグラフィ等で確認しておくことも大切です。
全館空調でゴキブリは出ますか?
全館空調でもゴキブリが出る可能性はありますが、全館空調が直接ゴキブリの発生原因になることはありません。むしろ、空調設備が少なく外部との接続が少ない全館空調の場合、出にくいとも言えます。そのため、定期的な掃除、室内の湿度管理、食べ物の管理、ダクト清掃の徹底など基本的な管理が効果的な予防策になります。
全館空調の冬の電気代はいくらですか?
住まいの断熱性能・家族構成・延床面積・使用するシステムによって異なりますが、高断熱・高気密住宅であれば、月平均1〜2万円程度に抑えられるケースが多いです。ただし、古い家や断熱性能が低い家では電気代が高くなる傾向があるため、住宅性能が重要です。
後から温度調整の設備を追加することはできますか?
後から温度調整の設備を追加することはできません。但し、補助的にサーキュレーターやエアコンを追加する、またはダクトやファン、温度センサーを再配置するリフォームを行うことで、住みながら調整をしていくことができます。ただし、大規模な調整は費用がかかるため、やはり新築時の計画が非常に重要です。